ジョイビジョン奈良・Opt Matsumotoは、両眼視機能評価・視覚認知評価・感覚統合・心理学の知見をもとに、“本当に必要な眼鏡”を提��案する専門店です。

- ジョイビジョン奈良・Optmatsumoto - joyvision-nara
▪️マーシャル・B・ケッチャム大学 TOCエグゼクティブ認定プログラム修了
▪️米国ケッチャム大学/TOC上級通信講座 修了
▪️国家検定資格.1級.眼鏡作製技能士
▪️作業療法士(発達領域)による評価も可能です
奈良県 橿原市 常盤町495-1
営業時間9:30~19:00
水曜定休/八重山諸島出張の場合、連休
TEL 0744-35-4776(完全予約制)
視覚認知検査 & 視覚発達支援
〜発達障害・視知覚・視覚機能の発達が気になるお子様へ〜
(完全予約制及び完全紹介性)
🕊ご案内とお願い
発達や視覚認知の検査は、非常に繊細で丁寧な評価が必要となるため、当店では医療・教育・療育機関など専門支援者からのご紹介を通してお受けしております。
ご紹介の際は、学校・療育施設・医療機関などのご担当者様から、お電話またはメールにて事前の情報共有をお願いいたします。
(対象者さまご本人・保護者さまからの直接予約はお受けしておりません)
🌱私たちの思い
お子さまの“困りごと”を、誰かの“せい”にせず、一緒に構造を見つけていくこと。
それが、ジョイビジョン奈良の発達支援における基本姿勢です。
【重要】小・中学校及び療育施設からのご紹介方法についてのお願い
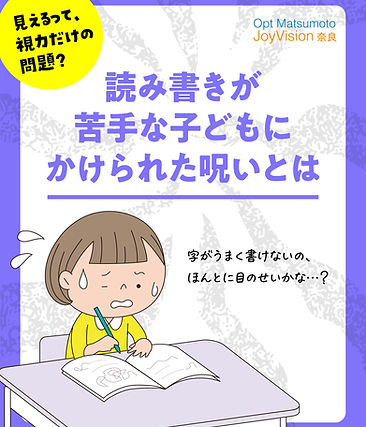

視覚認知検査 & 発達支援
〜見え方と発達の“ズレ”を理解し、支援につなげる〜
(完全予約制・紹介制)
1|まずお伝えしたいこと
発達や視覚に関する困りごとは、単なる「視力」や「行動の問題」ではなく、“見え方・感じ方・理解のつながり”のズレから生まれることがあります。
ジョイビジョン奈良では、そうしたズレを“構造”として理解し、そのお子さまにとって一番自然な見え方・関わり方を一緒に探していきます。
そのため、医療・教育・療育機関などの支援者さまからのご紹介を通してのみ検査を行っています。
2|対象と連携方針
以下の機関との連携を優先しています。
(お子さまの状態により、より適切な機関をご案内する場合があります)
-
医療機関(小児精神科・心療内科など)
-
教育関係機関(学校・特別支援教育など)
-
療育・支援関係機関
※発達領域に関する評価は平日のみ実施しております。
3|ご紹介から検査までの流れ
ジョイビジョン奈良では、「正確な評価」と「安心できる支援連携」を大切にしています。
ご紹介時は、次の流れに沿って進めていただいております。
① ご紹介者(学校・施設・専門職)からのご連絡
お子さまの様子・検査結果(例:WISC・K-ABC2など)・支援方針などをメールまたはお電話にてお知らせください。
📧 joyvisionnaraoptmatsumoto@gmail.com
📞 0744-35-4776
② 情報確認と対応可否のご連絡
内容を確認のうえ、対応可能な場合は保護者さま専用フォームをお送りします。
③ 保護者さまによるフォーム入力
お名前・年齢・困りごと・希望日程などを記入して送信していただきます。
④ ご予約確定
確認後、当方より日時確定のご案内をお送りします。
この時点でご予約完了となります。
4|費用と内容について
評価・カウンセリングを含めた包括的支援費用として、18,000円(税込)を頂戴しております。
内容には以下を含みます:
-
両眼視機能・視覚認知評価
-
感覚プロファイルの分析
-
読み書き・姿勢など日常動作への影響分析
-
背景要因や感覚特性の聴取カウンセリング
-
必要に応じたトレーニング・療育的助言
-
医療・教育機関への橋渡しや報告
5|担当者紹介
松本 康志
ジョイビジョン奈良.OptMatsumoto代表
国家資格1級眼鏡作製技能士
米国ケッチャム大学TOC上級講座 修了
松本 竜久(リク)
国家資格 作業療法士(発達領域)
視機能×作業療法による発達支援専門
教育現場・学会・研修講師として多数の登壇実績あり。
詳細な経歴は下段をご覧ください。
6|協働と信頼のネットワーク
以下の機関・専門家と連携体制を整えています。
(紹介時の情報共有は不要です)
-
一般社団法人LITTO-LABO 子どもの心理・教育研究所「ひかり塾」
-
奈良県立医科大学 精神科 水井先生
-
児童家庭支援センターあすか
-
放課後等デイサービス FLOW
-
他、当方が直接信頼関係を築く作業療法士・ST・PT・臨床心理士・教員 等
7|私たちの想い
“検査”は、理解の入口であって、評価のゴールではありません。
「できない」を責めず、「どうすればできるか」を一緒に考える。
それがジョイビジョン奈良の発達支援です。
📅 発達領域に絡む視知覚評価は平日のみの実施です
【資格・専門領域】
✅ 国家資格 作業療法士(発達領域専門)
✅ 視機能と作業療法の専門知識を活かした発達支援
【経歴】
2021年国家資格・作業療法士取得
📌 2023年:奈良県立教育研究所にて 「視覚機能と作業療法」 を講演
📌 2024年:第58回日本作業療法学会(札幌コンベンションセンター)にて 「視覚機能関連への直接介入により学校での板書活動に改善が見られた事例」 をポスター発表
📌 2025年:奈良市・京西中学校にて 「感覚統合を軸にした視覚機能の理解と教育現場での実践」 の研修講師
📌 2025年:奈良市・椿井小学校にて 「周囲に気付かれにくい困り感を持つ児童の評価と、それに基づいた介入例」 の研修講師
📌 2025年:奈良県・田原本南小学校にて 「学校現場でできる視覚関連機能の評価と事例紹介を通してOT評価の視点」 の研修講師
📌 2025年:奈良県・室生小学校にて「学校現場でできる視覚関連機能の評価と事感覚統合の視点」 の研修講師
📌 2025年:第二回「おもろいOTカーニバル」in大阪にて「視る力を見れるOTになりたい」をプレゼン。
🔹 視機能の知識・技術は、父であり当店代表の松本康志より、直接継承・研鑽を積んでおります。
📌 お子様の様子で、こんな心配はありませんか?
🔍 以下のようなサインが見られる場合、視覚認知や視機能の評価が役立つ可能性があります。
✅ 読むことの困難
• 文字を読むのに時間がかかる
• 行を飛ばしたり、同じところを繰り返し読んでしまう
• 文字が動いて見える
• 字を覚えにくい / よく似た字を混同する
✅ 書くことの困難
• 書くことを嫌がる / 字を書くのが苦手
• 文字をマスに収めることが難しい
• 鏡文字を書いてしまう
✅ 視覚過敏・視知覚の問題
• 白い紙に書かれた字を眩しがる
• 探し物をうまく見つけられない
• 図形の理解が苦手
✅ 空間認識・運動の困難
• 左右を認識しにくい
• 手先が不器用 / 身体を動かすことが不器用
📝 もしこれらのサインが当てはまるなら、“見る力”=ただ視力が良いことだけではなく、視覚情報の取り込み・処理・活用という構造にズレがある可能性があります。
📌 評価内容(詳細)
🔍 視機能・視知覚・動作・感覚の多層的な評価を実施
すべてのケースで全項目を実施するわけではありません。評価内容は、ご本人の状態や目的に応じて適切に抽出・選定して行います。
「すべての検査をやる=丁寧である」という文化的誤解もありますが、不要な評価は逆に負担になり、本質を見失わせる場合もあるため、過不足なく本質的な情報を得ることを重視しています。
🟢 視機能検査
• 両眼視機能の詳細な分析(眼位・輻輳/開散・調節機能)
• 視機能分析(ACA比・融像幅・フォロメトリーを含む)
• 眼球運動評価(対面法+DEM:Developmental Eye Movement Testの2種バッテリー)
🟢 視覚認知評価
• TVPS-4(Test of Visual Perceptual Skills-4)
• MVPT-4(Motor-Free Visual Perception Test-4)
• 視覚運動評価(VMI模写検査:Visual-Motor Integration)
🟢 視覚過敏性・感覚評価
• 視覚の過敏性・アーレンシンドローム評価
• 原始反射残存チェック(視覚機能との関連性を確認)
• 感覚プロファイル(視覚・聴覚・前庭覚・触覚を含む総合的評価)
🟢 動作・姿勢・環境要因の評価(作業療法士の勤務日に限る)
• 動作分析(書字・筆圧・姿勢・目と手の協応・視空間認知)
🟢 検査結果の総合解釈・支援方策
• 検査結果の統合分析と解釈
• 個別に適した眼鏡補正・トレーニング指導・環境調整の提案
⚠️ ただ多くの検査を行えば良い、というわけではありません。
“不要な評価”はお子さまにとって負担になり得ます。
当店では、目的に応じた適切な検査設計を重視し、過不足なく本質的な情報を得ることを大切にしています。
🌿 見ることの「改善」は、未来を見据えた選択から始まります
視機能や視覚認知の評価を行う際、最も重要なのは「解決志向」と「未来的思考」の視点を持つことです。
私たちは、「なぜこうなったのか?」という原因志向にとどまらず、「これからどうすればより良い方向に向かうのか?」という未来志向の戦略を重視しています。
そのために必要なのが、次の3つの考え方です。
🔹 1. 信頼関係の構築が、すべての出発点
検査の精度や方策の効果は、技術だけではなく、「検査者 × ご本人 × ご家族」の間にある信頼関係によって大きく左右されます。
そのため、私たちはまず「課題に対する合意」と「目標に関する合意」を大切にしています。
「検査を受ければ何か変わる」ではなく、「どう変えていくかを一緒に探す」―そんな姿勢で臨んでいただくことが、何よりも重要です。
✅ ご予約の前にご確認ください
-
「病院で言われたから、とりあえず…」
-
「受けたら何かわかるかも…」
といった受け身の状態でのご来店はおすすめできません。
目的を共有し、前向きに取り組むことでこそ、結果を最大限に活かすことができます。
※ 信頼関係が築けないと判断した場合には、ご予約をお断りさせていただくこともあります。
それは検査が「測定」ではなく、「未来への戦略を共に立てるプロセス」だからです。
🔹 2. 「平場性(ひらばせい)」を大切にした関係づくり
私たちは、支援や検査の場を「上下関係」ではなく、対話と共創の場として捉えています。
-
治す/治される
-
教える/教わる
-
支援する/支援される
そうした一方向の関係をできるだけなくし、お互いが意見を出し合いながら“より良い見え方”を共につくる。
それがジョイビジョン奈良の考えるフラットな関係性(平場性)です。
この関係が生まれたとき、本人の主体性が育ち、「できること」が自然に増えていきます。
🔹 3. 検査の目的は「困り感の可視化」ではなく、「方策の発見」
私たちが行う視機能・視覚認知検査は、現状を“見える化”するだけのものではありません。
-
どんな困りごとがあるのかを明確にする
-
それをどう改善し、生活に活かすかを考える
-
実際の行動や支援につなげる「方策」を見つける
検査のゴールは、“知ること”ではなく、“変わること”。
🔹 未来を見据えた「実践的な視点」へ
当店では、検査結果をもとに、視機能だけでなく感覚・心理・環境を含めた支援ストラテジーを提案しています。
たとえば、
-
現状の困り感を軽減する方法
-
将来的なリスクを予測して対策する方法
など、「今と未来の両方を支えるアプローチ」を大切にしています。
視ることを、単なる診断や補正ではなく、未来をつくる戦略として一緒に考えていきましょう。

視力だけでは測れない「両眼視機能」の本質
視機能とは「視力」だけを指すものではありません。
視力は視覚機能のごく一部であり、「見え方の質」を決定するのはむしろ両眼視機能や調節機能の状態です。
✔ 視力検査で「問題なし」と言われたのに、見えにくさや読み書きの困難がある
✔ 両眼視機能の不良が、学習・スポーツ・日常生活のパフォーマンスに影響している
このようなケースは少なくありません。
「視力が良いから大丈夫」という誤解
学校の視力検査や簡易的な視力測定では、**「単眼での視力」**しか評価しません。しかし、実際の「見る」という行為は、両眼を適切に連携させ、スムーズに焦点を合わせる機能(輻輳・調節・眼球運動)が整っているかどうかで決まります。
💡 視力1.0でも、両眼視機能の問題があれば…
✔ 文字がぼやけたり、二重に見えたりする
✔ 黒板の文字が読みづらい、ノートにピントを合わせるのに時間がかかる
✔ 文章を読むのに時間がかかり、行を飛ばしたり同じ行を繰り返してしまう
✔ スポーツでボールの距離感がつかみにくい
このような困り感があっても、単純な視力検査では検出されません。
視力が「A判定」でも安心できない理由
学校の視力検査は、あくまでスクリーニング目的の「ふるい分け検査」です。
✔ 「見える」か「見えないか」の基準で判断するため、微細な両眼視のズレや調節不良は評価されない
✔ 片眼ずつの測定のため、「両眼で見たときの問題」が見逃される
✔ 視力が1.0以上であれば「問題なし」と判断されるが、実際には視機能のトラブルが潜んでいることも多い
「視力が良い=見え方に問題がない」という考え方は、あまりにステレオタイプな発想であり、視機能の本質を捉えていません。
両眼視機能を評価することの重要性
✔ 斜位・斜視の有無と、その補正能力(融像力・輻輳力)の測定
✔ 調節機能(ピント調整力)の評価
✔ 眼球運動のスムーズさ、読み書きへの影響を分析
✔ 両眼視機能が学習・スポーツ・日常生活にどのような影響を与えているかを総合的に判断
これらを詳細に検査しなければ、視力検査では見えない「本当の見え方の問題」は見えてきません。

光の感受性障害・アーレンシンドローム・視覚過敏の問題
視力や両眼視機能に問題がなくても、「文字が揺れて見える」「文章が波打つ」「文字が反転して見える」「紙面が光って見える」といった視知覚に関連した障害に悩まされる方がいます。
このような症状は、アーレンシンドローム(Irlen Syndrome)、ミアーズ・アーレンシンドローム(Meares-Irlen Syndrome)、または**視覚ストレス(Visual Stress)**と呼ばれる光の感受性障害に関連している可能性があります。
アーレンシンドロームとは?
アーレンシンドロームは、視力や眼球運動だけの問題ではなく、中枢領域での神経伝達の異常によるものと考えられています。
この状態にある方は、通常の文字や印刷物を見るだけでも脳が過剰に情報を処理しようとして負担がかかり、視知覚に歪みや違和感が生じることが特徴です。
💡 主な症状の例
✔ 文字が揺れたり、にじんだり、反転して見える
✔ 行を飛ばしてしまう、読んでいる途中で文章を見失う
✔ 紙の白い部分が光ってまぶしく感じる
✔ 文章が波打って見えたり、背景がチカチカする
アーレンシンドロームの有症率は、欧米では20%~38%、日本では約6%と推定されています。しかし、日本ではアセスメントを実施できる機関が限られており、認知度が低いのが現状です。
アーレンシンドロームのサブタイプ分類と対応
当店では、アーレンシンドロームを以下の4つのサブタイプに分類し、それぞれに適したアプローチを行っています。
1️⃣ 視機能不良型
👉 両眼視機能の問題(斜位・調節不良・眼球運動の異常)が原因
✅ 両眼視機能検査で評価し、適切な視機能補正を行う
2️⃣ 感覚過敏型
👉 光に対する感受性が極端に高く、視覚刺激に過剰反応する
✅ 特殊フィルター(カラーグラス)の調整で軽減
3️⃣ 高次眼収差型
👉 角膜・水晶体・網膜のわずかな歪みが原因で視知覚に影響
✅ 特殊設計レンズによる収差補正で改善
4️⃣ 重複型
👉 上記の複数要因が絡み合っているケース
✅ 総合的なアセスメントを行い、個別の方策を立案
「光がまぶしい=アーレンシンドローム」ではありません。
適切なアセスメントなしに、単に「眩しいからカラーグラスを入れる」という対処は不適切な場合もあります。
当店でのアプローチ
当店では、オプトメトリー(視機能学)の視点から、光感受性の問題を精密検査で分類し、それぞれに適した対策を提案します。
単なる「カラーグラスを入れる」だけではなく、視機能・視知覚・感覚処理の複合的な要素を統合したアプローチを行い、より効果的な解決策を提供します。
💡 アーレンシンドロームや視覚過敏にお悩みの方は、ぜひ詳細なアセスメントを受けてみてください。

眼球運動の正確性と学習・生活への影響
眼球運動は、読み書き・スポーツ・空間認識など、学習や日常生活に必要不可欠な能力です。
視力が1.2あったとしても、眼球の動きをスムーズに制御できなければ、**「よく見えるはずなのに読みにくい」「文字を見失う」「スポーツでの動体視認が苦手」**といった困り感につながります。
当店では、眼球運動能力を標準化されたデータと比較し、精密に評価することで、お子さんの眼球運動スキルの状態を可視化します。
眼球運動評価の方法
当店では、以下の2つの標準化された評価法を用いて、眼球運動のスキルを精査します。
✅ SCCO4+(対面法評価)
👉 眼球運動の質的評価(追従性・跳躍性・固視能力)
✅ DEM(Developmental Eye Movement Test)
👉 眼球運動の量的評価(視線のスムーズさ・視点移動の速度)
この質的・量的な両方の分析を行うことで、眼球運動スキルの問題をより明確にし、学習や日常生活への影響を正確に把握します。
眼球運動の弱さがもたらす困難
👀 眼球運動スキルが未熟な場合、以下のような困り感が生じることがあります。
✔ 読書・板書の困難
・行を飛ばしてしまう
・文字を目で追うのが遅い
・視線を素早く移せず、読み飛ばしが多い
✔ スポーツでの苦手感
・ボールの動きを正しく追えない
・距離感やスピードの把握が難しい
・素早い動きについていけず、プレーに遅れが出る
✔ 日常生活での影響
・黒板やホワイトボードを写すのに時間がかかる
・探し物が苦手(視線を素早く動かせないため)
・目の疲れや頭痛が起こりやすい
改善のためのアプローチ
当店では、眼球運動の弱さの背景に視力・視機能の問題がある場合は、眼鏡補正を行ったうえで、トレーニングを実施します。
また、視力や視機能に問題がなく、眼球運動スキルのみに未熟さが認められる場合は、眼球運動や粗大運動を含めたトレーニングで改善を目指します。
💡 眼球運動トレーニングのイメージ
眼球運動スキルの向上は、「水泳の習得」や「自転車に乗ること」の習得過程に非常に似ています。
一度スキルが獲得できれば、大人になってもそのスキルは保持されるため、早期に適切なトレーニングを行うことが重要です。
「見る力」を鍛えることで、学習やスポーツの困り感を軽減!
眼球運動のスキルは、学習・スポーツ・日常生活のあらゆる場面で重要な役割を果たします。
「視力には問題がないのに、なぜか読み書きが苦手」「スポーツがうまくできない」と感じる場合、視機能や眼球運動の評価を受けることで、根本的な原因を特定し、最適なサポートが可能になります。

調節力の柔軟性:視覚のピント調整機能とその重要性
人の目は、遠くを見るときには水晶体を緩ませ、近くを見るときには水晶体を膨らませることで、ピントを調整しています。このピント調整能力を**「調節力」**と呼びます。
調節力には年齢ごとの標準範囲があり、高すぎても低すぎても視覚の負担につながります。
また、加齢による調節力の減少はよく知られていますが、子どもでも遠視の未補正や調節力のアンバランスによって、学習や日常生活に影響を及ぼすことがあります。
調節力の低下や柔軟性不足がもたらす困難
👀 調節力に問題がある場合、以下のような困難が生じることがあります。
✔ 視線移動時のピント合わせが遅い・難しい
・黒板の文字を見てからノートに視線を移すと、ピントが合うのに時間がかかる
・本を読んでいて、次の行に移るたびに文字がぼやける
✔ 長時間の読書や学習が疲れやすい
・長時間本を読むと目がかすむ・疲れやすい
・板書やパソコン作業の際、目の奥が痛くなる
✔ 近視化や仮性近視のリスク
・ピントを近くに合わせる筋肉(毛様体筋)が緊張しすぎることで、一時的な近視状態に陥る
・本来の屈折異常と異なる状態で視力が低下する
✔ スポーツや日常生活での困り感
・ボールを遠くから近くに追うとき、ピントがスムーズに合わない
・近くのものを見たあとに遠くを見たとき、ぼやけが続く
調節力の詳細な評価と介入
当店では、以下の方法を用いて調節力を詳細に評価し、最適な介入方法を提案します。
✅ 単眼・両眼での調節評価
👉 各眼ごとの調節力の測定(片目の調節力と両眼での調節のバランスを比較)
✅ 動的な調節力評価(動的調節機能検査)
👉 視線移動時の調節速度・柔軟性の評価(遠近のピント移動のスピードと精度を分析)
✅ ACA比(調節と輻輳のバランス評価)
👉 調節と輻輳の連携状態を数値化し、適切な補正方法を検討
✅ 調節幅と調節ラグの分析
👉 調節力の過不足や調節のタイミングのズレを評価し、視覚疲労の原因を特定
調節力に問題がある場合の対応
調節力の問題がある場合、以下の方法で改善を図ります。
🔹 眼鏡補正による視機能の正常化
→ 適切な度数補正を行うことで、調節力の負担を軽減し、快適な見え方を確保
🔹 調節トレーニング(オプトメトリックリハビリテーション)
→ 調節力が低下している場合、特定の視覚トレーニングを実施することで、調節力の回復を図る
🔹 環境調整(照明・作業距離の最適化)
→ 照明の工夫や適切な作業距離の確保により、調節力への負担を軽減
「見る」ことの負担を軽減し、より快適な視覚環境へ
調節力の柔軟性は、学習・仕事・スポーツ・日常生活に大きく関わる要素です。
「疲れやすい」「視線移動でピントが合いにくい」「文字がにじむ」といった症状がある場合、視力だけではなく、調節力の詳細な評価が必要です。

輻輳・開散運動の柔軟性:両眼のチームワークと視覚の安定性
「遠くを見る」「近くを見る」だけではなく、視線移動のスムーズさが重要です。
人間の視覚は、ただ単に「遠方を見る」「近方を見る」という1か0の動きではなく、その間の無数の視線移動がスムーズに行われることが求められます。その鍵となるのが、輻輳(内寄せ)と開散(外寄せ)の柔軟性です。
輻輳・開散とは?
👀 輻輳(内寄せ)
👉 近くのものを見るときに、両目を内側に寄せる動き
📌 例:本を読む・ノートを書く・スマホを見る
👀 開散(外寄せ)
👉 遠くを見るときに、両目を外側に向ける動き
📌 例:黒板を見る・スポーツで遠くのボールを追う・運転時の道路確認
輻輳・開散に問題があると?
🔹 学習・仕事の困難
✔ 近くの文字にピントを合わせ続けるのがつらい
✔ 黒板→ノートの視線移動がスムーズにできない
✔ PC作業で長時間画面を見ていると、目の奥が痛い
🔹 スポーツ・運転の困難
✔ 球技でボールの距離感がうまくつかめない(バスケ・野球・テニス・サッカーなど)
✔ 車の運転時に、前方とサイドミラーの視線移動がスムーズにできない
🔹 生活への影響
✔ 遠くの標識や看板がぼやけて見える
✔ 買い物時に商品がすぐに見つからない
輻輳・開散の評価方法
✅ 近方視と遠方視の評価
👉 遠方・近方の輻輳・開散能力をチェックし、視線移動のスムーズさを分析
✅ NPC(近点輻輳)の測定
👉 どれくらい近くまでピントを合わせ続けられるかを評価
✅ AC/A比(輻輳と調節のバランス)
👉 調節と輻輳の連携が適切に機能しているかを数値化
✅ 融像幅の測定
👉 両眼がどの範囲まで快適に協調できるかを評価
改善のためのアプローチ
🔹 眼鏡補正
適切なプリズム処方や両眼視のバランスを考慮した眼鏡で、負担を軽減
🔹 視覚トレーニング
眼球の動きを強化し、視線の移動やピント合わせのスムーズさを改善
🔹 環境調整
学習・作業環境を整えることで、視覚負担を軽減
「見えにくさ」に気づきにくいからこそ、評価が重要
輻輳・開散の問題は、本人が自覚しにくいことが多いため、「見えているのに疲れる」「視線移動が苦手」「球技や運転がうまくいかない」といったサインを見逃さないことが大切です。
「目が悪いわけではないけど、なんとなく見づらい」と感じる方は、一度視機能の精密な評価を受けることをおすすめします。
感覚プロファイルでわかること

― あなたの見え方、感じ方は本当に「普通」? 感覚の偏りがもたらす影響を知る ―
人の「感覚」とは、視覚・聴覚・前庭覚・触覚・複合感覚・口腔覚など、私たちの周囲の情報を受け取るための重要なシステムです。しかし、これらの感覚の受け取り方は個人差が大きく、「普通」と思っていることが、他の人にとっては大きな負担になっている可能性があります。
感覚処理に偏りがある人の困難さは、他者には理解されにくく、「気のせい」「慣れれば平気」と軽視されがちですが、実際には行動や情動反応に大きな影響を与えるため、包括的に把握することが重要です。
たとえば、
✅ 極端に眩しがる
✅ 人混みが苦手でフラフラする
✅ 視力は問題ないのに見えにくさを訴えない
✅ 乗り物に酔いやすい
これらは、単なる「体質」ではなく、**感覚の過敏さや低反応(鈍麻)**が関係している可能性があります。
なぜ感覚プロファイルが必要なのか?
感覚の偏りがある場合、環境における刺激量を適切に把握しないまま生活を送ると、
❌ 耐えがたい苦痛を感じることがある
❌ 十分な感覚刺激を得られず、必要な反応ができない
❌ 視力や眼鏡補正の効果が十分に発揮されない
そのため、当店では単なる視力検査ではなく、感覚刺激への生体反応を客観的にプロファイリングし、視機能・視覚認知・感覚処理を総合的に解析するアセスメントを導入しています。
感覚プロファイルの4つの象限
感覚特性は「低登録」「感覚探求」「感覚過敏」「感覚回避」の4つの象限に分類されます。
これを知ることで、自分やお子さんの感覚の特性を正しく理解し、最適な環境調整やサポートが可能になります。
1️⃣ 低登録(Low Registration)
【特徴】
✔ 気づきが低い(神経学的閾値が高い)
✔ 感覚刺激に気づきにくい or 反応が鈍い
✔ 受動的な行動が多い
【具体例】
• 相手の声が聞き取りづらく、聞き返すことが多い
• 怪我をしても痛みに気づかない
• 皮肉や冗談が通じにくく、暗黙のルールを察するのが苦手
• 顔や体の汚れに無頓着
• 探し物や案内標識を見落としやすい
🔹 解決策
• 視覚的な情報提示を増やし、コントラストを強調
• 重要な情報は言葉だけでなく、ジェスチャーや実物を見せて伝える
• 身の回りのものを整理し、視覚的な手がかりを増やす
2️⃣ 感覚探求(Sensation Seeking)
【特徴】
✔ 神経学的閾値が高いが、刺激を求める
✔ じっとしているのが苦手
✔ 感覚を満たすために能動的に行動する
【具体例】
• じっとしているのが苦手で、ソワソワ動き回る
• 高いところに登ったり、飛び跳ねたりする
• 一人で回転する、走り回ることが多い
• 物の扱いが雑になりやすい
🔹 解決策
• 感覚刺激が入る活動をスケジュールに組み込む(例:トランポリン、スイング)
• 身体を動かすタイミングを意図的に作る(例:授業前にジャンプ運動を行う)
• 不適応行動を適応的な代替行動に変える(例:机の上で足を揺らす代わりにストレスボールを握る)
3️⃣ 感覚過敏(Sensory Sensitivity)
【特徴】
✔ 神経学的閾値が低く、過剰に感覚を受け取る
✔ 刺激に対して恐怖や不快感を抱きやすい
✔ 静かで落ち着いた環境を好む
【具体例】
• 大きな音に耳をふさぐ
• 触られるのを嫌がる(特に不意に触られると驚く)
• 手が汚れることを極端に嫌がる
• 蛍光灯やLED、日の光を極度に眩しがる
• 不安定な遊具(ブランコなど)を避ける
🔹 解決策
• 過敏な刺激を軽減する(例:ノイズキャンセリングイヤホン、遮光レンズ、ブルーライトカットレンズ)
• 環境の調整(例:照明の調整、静かなスペースの確保)
• 感覚刺激のコントロール訓練(例:触れることに慣れるトレーニング)
4️⃣ 感覚回避(Sensation Avoiding)
【特徴】
✔ 神経学的閾値が低く、刺激を避けるために能動的に行動する
✔ 苦手な刺激から逃れるために積極的に回避行動をとる
✔ 刺激が多い環境を避けがち
【具体例】
• 大きな音がなると部屋から出ていく
• 苦手な刺激のもとになっている人や物をたたいたりする(小さい子に多い)
• 薄暗い部屋でじっとしていることが多い
🔹 解決策
• ストレスを軽減するための回避戦略を用意する(例:サングラス、耳栓、特定の素材の服を避ける)
• 感覚回避の理由を周囲が理解し、強制しない
• 少しずつ慣れるトレーニングを行うが、無理に「慣れさせよう」としない
感覚プロファイルを活用することでできること
✅ 原因を正しく理解し、困り感を軽減できる
✅ 環境調整や補助ツールを使うことで生活の質を向上させる
✅ 本人の感覚特性に合った学習・仕事環境を整えられる
✅ メガネの度数やレンズ選びにも応用し、より快適な視覚体験を提供できる
「気のせい」「慣れれば平気」ではなく、感覚の特性を知ることで、より良い見え方・暮らし方へとつなげていきましょう。
TVPS-3で分かること(視覚認知)

1️⃣ 視覚弁別(Visual Discrimination)
― 似たものを正しく見分ける力 ―
視覚弁別とは、類似した視覚対象の中から細部の違いを見分ける能力です。
この能力が弱いと、文字や図形の細かな違いに気づきにくく、書字や読解に困難が生じることがあります。
✅ 視覚弁別が弱いと現れる特徴
• よく似た漢字や文字を間違える(例:「午」と「牛」、「未」と「末」)
• 線の本数や構成の違いが分かりにくい(例:「書」と「署」、「棒」と「傍」)
• アルファベットの形を混同する(例:「b」と「d」、「p」と「q」)
• 数学の記号(+と×、-と=)を間違えやすい
• 定規を使う学習や、図形のトレースが苦手
✅ 視覚弁別が弱いと影響する学習領域
• 漢字の学習(部首の違いを見分ける)
• 算数(数字や記号の識別)
• 板書(ノートに正しく書き写す)
• 工作や美術(形の細部を正確に認識する)
✅ 視覚弁別を向上させるトレーニング
• 間違い探しや影絵クイズを取り入れる
• 線の違いを意識した漢字の練習(部首ごとに色を変えるなど)
• 図形のトレースや迷路、パズルを活用する
• 視覚的な情報を整理する習慣をつける(色分け、下線を引くなど)
視覚弁別の問題は**「不注意」ではなく、認知的な特性として捉えることが重要**です。
学習環境の調整やトレーニングを通じて、苦手を克服するサポートをしていきましょう。

2️⃣ 視覚記憶(Visual Memory)
― 見たものを覚えて再現する力 ―
視覚記憶とは、視覚的な情報を一時的に記憶し、それを再現する能力です。
この能力が弱いと、見たものを正しく思い出せず、学習や運動に影響が出ることがあります。
✅ 視覚記憶が弱いと現れる特徴
• 板書が遅い・ミスが多い(黒板を見ている間は覚えているが、ノートに書くときに忘れてしまう)
• 新しい漢字や単語がなかなか覚えられない(一度見た字をすぐ忘れる)
• 絵や図の細かい部分を再現できない(模写が苦手)
• 読み書きの際に文字を見失いやすい(行を飛ばしたり、同じ行を繰り返し読む)
• 地図やルートを覚えるのが苦手(一度通った道を思い出せない)
✅ 視覚記憶が弱いと影響する学習領域
• 国語(漢字や文章の記憶・定着)
• 算数(図形問題や計算式を覚える)
• 理科・社会(図表や地図の理解)
• スポーツ(動きのパターンを覚えて再現する)
✅ 視覚記憶を向上させるトレーニング
• フラッシュカードを使った学習(漢字や単語を素早く記憶)
• 図形パズルや迷路遊び(形や配置を覚える練習)
• マインドマップや図解を活用した学習(視覚情報を整理する)
• 短時間で視覚情報を記憶し、それを再現するゲーム(神経衰弱や記憶テスト)
視覚記憶が弱いお子さんに対しては、情報を整理して覚えやすくする工夫や、記憶を補助するツールを使うことが効果的です。
学習の苦手を単なる「努力不足」ではなく、認知特性として捉え、適切なサポートを行いましょう。

3️⃣ 空間関係(Spatial Relations)
― 物の位置や向きを正しく認識する力 ―
空間関係とは、物の位置関係(上下・左右・前後)や、形の向きを正しく捉える能力です。
この能力が弱いと、文字や図形の向きを誤認したり、体の動きを空間に適応させることが難しくなることがあります。
✅ 空間関係が弱いと現れる特徴
• 鏡文字を書く(小学校2年生以上になっても「5」や「さ」などが逆向きになる)
• 文字の向きを間違える(「b」と「d」、「6」と「9」を混同する)
• 漢字の書き順や構成を理解しにくい(「日」と「目」などの違いが分かりにくい)
• 上下・左右・前後の区別が苦手(「右手をあげて」と言われても混乱する)
• 地図やグラフを読み取るのが苦手(方向や位置関係を把握しづらい)
• 体育や球技でのポジショニングが難しい(キャッチボールやサッカーでボールの動きを予測できない)
✅ 空間関係が弱いと影響する学習領域
• 国語(文字の認識・書字)
• 算数(図形問題・グラフの理解)
• 体育(空間認識を伴う動作やスポーツ)
• 美術(デッサンや工作での形の再現)
✅ 空間関係を向上させるトレーニング
• 迷路やパズル遊び(空間配置の理解を強化)
• 折り紙や積み木遊び(立体の形を把握する練習)
• 手指を使ったボディマッピング(自分の体の左右・上下を意識する)
• 運動を通じた空間認識トレーニング(球技や縄跳びで動きの予測力を鍛える)
空間関係の認識が苦手なお子さんには、視覚的なフィードバックを活用しながら、具体的な経験を積ませることで、認識力を向上させることができます。
また、単なる「不器用」として片付けず、視覚認知の課題として捉え、適切なサポートを行うことが重要です。

4️⃣ 形の恒常性(Form Constancy)
― 形が変わっても同じものと認識する力 ―
形の恒常性とは、向きや大きさが異なっていても、同じ形や文字として認識する能力です。
この能力が弱いと、視覚情報の変化に適応しにくくなり、文字の読み間違いや書き間違い、学習の遅れにつながることがあります。
✅ 形の恒常性が弱いと現れる特徴
• 黒板の字とノートの字の大きさが違うと、同じ文字と認識できない
• 異なるフォントの文字を判別しにくい(「a」と「𝒶」、「G」と「𝓖」が同じ文字とわからない)
• 手書きと印刷された文字の区別が難しい(活字の「き」と手書きの「き」を別のものと認識してしまう)
• 図形の大きさや向きが違うと、同じ図形と気づかない(小さな三角形と大きな三角形を異なる形と見なす)
• ひらがなや漢字の習得が遅れる(「田」と「由」などの似た字の識別が苦手)
• 算数の図形問題で混乱しやすい(「直角三角形」と「斜めになった直角三角形」が同じ形と認識できない)
• 看板や標識のデザインが変わると、何のマークかわからなくなる
✅ 形の恒常性が弱いと影響する学習領域
• 国語(文字の認識・書字・読解力)
• 算数(図形問題・パターン認識)
• 理科(グラフや図表の理解)
• 社会(地図や年表の認識)
✅ 形の恒常性を向上させるトレーニング
• さまざまなフォントで同じ単語を読む練習
• 異なるサイズ・向きの図形を同じものとして分類するゲーム
• 影絵やシルエットクイズで形を認識するトレーニング
• 折り紙やパズルを使い、形の変化を楽しみながら学ぶ
形の恒常性の課題は、日常生活の中で視覚情報を適切に処理する上で重要なスキルです。
読み書きの困難さや学習の遅れが見られる場合は、形の認識に苦手さがあるかどうかをチェックし、適切なトレーニングや環境調整を行うことが大切です。
5️⃣ 視覚連続記憶(Sequential Memory)
― 順序や系列を記憶する力 ―
視覚連続記憶とは、複数の視覚情報を順番通りに記憶・再現する能力を指します。
一般的な短期記憶(Visual Memory)は単一の視覚情報を記憶する能力ですが、視覚連続記憶は複数の視覚情報を「順番通りに」覚える能力が求められます。
例えば、
✅ 短期記憶(Visual Memory)
→ 「一つの漢字や単語を記憶して再現する」
✅ 視覚連続記憶(Sequential Memory)
→ 「文字や図形を順番通りに記憶し、正確に再現する」
この能力が弱いと、学習や日常生活で困難を感じる場面が多くなることがあります。
✅ 視覚連続記憶が弱いと現れる特徴
• 黒板の板書を順番通りにノートに書き写せない
• ひらがなや漢字の「書き順」を覚えにくい
• 英単語や文章を順番通りに記憶するのが苦手(「apple」と「alppe」を混同する)
• 数字の並び順を間違えやすい(電話番号や暗証番号を覚えにくい)
• 算数の筆算で、計算の順番を間違えやすい
• 工作や料理の手順を順番通りにこなせない
• スポーツのフォーメーションや動作の流れを覚えるのが苦手
✅ 視覚連続記憶が弱いと影響する学習領域
• 国語(漢字の書き順・文章の読解)
• 英語(スペリング・単語の記憶)
• 算数(筆算・数列の記憶)
• 社会(年号の順番・歴史の流れ)
• 音楽(楽譜の読み取り・リズムの記憶)
✅ 視覚連続記憶を向上させるトレーニング
• フラッシュカードを使い、順番通りに記憶する練習
• ブロックや積み木で「見た順番通りに並べる」トレーニング
• ひらがな・漢字の書き順をゲーム形式で学ぶ
• 文章を分割し、順番通りに並べる練習
• ダンスや体操の連続動作を覚えるトレーニング
視覚連続記憶は、学習や日常生活の手順をスムーズに進めるために必要なスキルです。
このスキルが弱いと「やることの順番を覚えられない」「文字や数字の並びを間違える」といった困難が生じますが、適切なトレーニングによって向上させることが可能です。

6️⃣ 図地弁別(Figure-Ground Perception)
― 必要な情報を見つける力 ―
人間の視覚システムは、目に入るすべての情報を処理するわけではなく、「必要な情報(図)」と「背景(地)」を分けて認識する仕組みになっています。
例えば、
✅ 教科書の文字を読むとき → 文字(図)を識別し、背景(白紙)は抑制する
✅ 黒板の文字を読むとき → 板書(図)を識別し、周囲の飾りや掲示物(地)を無視する
✅ 机の上で消しゴムを探すとき → 必要なもの(図)を見つけ、他の物(地)をフィルターする
この能力が弱いと、周囲の不要な視覚情報(地)に注意が向きすぎてしまい、必要な情報(図)を見つけにくくなるという問題が生じます。
✅ 図地弁別が弱いと現れる特徴
• 雑然とした教室で集中できない(掲示物や周囲の視覚刺激に気を取られる)
• 机の上やカバンの中で目的のものを探すのが苦手
• 黒板の文字を読むのに時間がかかる(余計な情報に目が行く)
• プリントや教科書の重要なポイントを見つけにくい
• 漢字の画数が多いと識別しにくい(文字の構造が埋もれる)
• 混み合った絵や写真から、目的のものを素早く見つけるのが苦手
• 迷子になりやすい(周囲の情報に圧倒され、目的の方向を見失う)
• スポーツのプレー中、相手やボールの動きを見極めにくい
✅ 図地弁別が弱いと影響する学習領域
• 国語(文章の要点を見つけにくい、漢字の細部を見分けにくい)
• 算数(数字や記号を見落としやすい、グラフや表を読み取りにくい)
• 理科・社会(図や写真から情報を抜き出しにくい)
• 英語(単語のスペルの識別が苦手)
• 体育・スポーツ(相手やボールの位置を見極めにくい)
✅ 図地弁別を向上させるトレーニング
• 間違い探しやパズル(類似した絵の違いを見つける)
• 迷路やウォーリーを探せ系のゲーム(目的の対象を見つける練習)
• プリントや教科書に「ハイライト」を入れる(重要情報を強調)
• 机の上や引き出しの整理を習慣化(視覚的な情報を減らす)
• 黒板の文字を追う際、指でなぞりながら読む(視線のガイドを作る)
図地弁別は、学習だけでなく、日常生活やスポーツ、仕事の場面でも重要なスキルです。
この能力を強化することで、必要な情報に素早くアクセスできるようになり、学習効率や生活のスムーズさが向上します。

7️⃣ 図形閉合(Visual Closure)
― 不完全な情報から形を完成させる力 ―
図形閉合(Visual Closure)とは、部分的に欠けた図形や文字を見て、それが何の形かを推測し、脳内で補完する能力です。
例えば、
✅ 破れた看板の文字を見て、何と書かれているかを推測する
✅ 車の後部しか見えていなくても、全体の形を想像して車種を識別する
✅ 漢字の一部が隠れていても、どの漢字かを推測する
✅ 行間の狭い文章でも、文字の形を認識しやすくする
この能力が弱いと、形を認識する際に「部分から全体を作る」プロセスが苦手になり、視覚的な情報処理に遅れが生じることがあります。
✅ 図形閉合が弱いと現れる特徴
• 文字を読み取るのが遅い(特に行間が狭い文章やフォントが異なる場合)
• 漢字を覚えにくい(部首や構成の識別が難しい)
• 書き写しのミスが多い(部分的に欠けた情報を補完しにくい)
• 計算の途中式で数字の認識ミスが起こりやすい
• 黒板の文字が一部隠れていると、全体の内容を推測しにくい
• 図やグラフの線が途切れていると、意味を理解しにくい
• パズルや間違い探しが苦手(部分的な違いを見つけにくい)
• 道路標識や地図の読み取りが苦手(欠けた情報を補完しにくい)
• スポーツで相手の動きを予測するのが苦手(部分的な情報から全体を把握しにくい)
✅ 図形閉合が弱いと影響する学習領域
• 国語(文字の識別が遅れる、漢字を覚えにくい)
• 算数(数字の認識が遅れる、途中計算の見間違いが多い)
• 理科・社会(グラフや図表の一部が欠けると意味が分からない)
• 美術・デザイン(完成図を想像するのが苦手)
• 体育・スポーツ(相手の動きを予測しにくい、ボールの軌道を把握しにくい)
✅ 図形閉合を向上させるトレーニング
• 図形の完成パズル(部分的に欠けた図を見て、全体を想像する練習)
• かすれた文字やフォントの違う文字を読む練習
• クロスワードやクイズ(欠けた情報を補完する能力を鍛える)
• 文章の一部を隠して読ませるトレーニング
• 図形や写真の一部を見せ、全体を推測するゲーム
図形閉合の能力が向上すると、視覚情報の認識速度が上がり、学習効率や日常生活のスムーズさが向上します。
また、スポーツや仕事の場面でも、**「部分的な情報から全体像を素早く理解する力」**が鍛えられ、パフォーマンス向上につながります。

視覚運動協応(VMI)とは?
VMI(Visual-Motor Integration)模写検査は、視覚情報を正しく認識し、それを手の運動に正確に変換する能力を測定する検査です。
つまり、「目で見たものを正確に手で書き写す力」を評価するものであり、書字・図形描写・工作・スポーツなどの技能に直結します。
✅ VMIが弱いと現れる特徴
• 字を書くときに形が崩れる(バランスが取れない、はみ出す、線が曲がる)
• 漢字の書き順や線の交差が正確でない
• 板書が苦手(黒板の文字を写すのに時間がかかる、正しく模写できない)
• 定規を使っても線が歪む、図形を描くのが苦手
• 工作や折り紙が苦手(手と目の連携がうまく取れない)
• スポーツでタイミングが合わない(ボールの動きを見て手を動かすのが苦手)
✅ VMIの弱さの背景
視覚運動協応の弱さは、以下の2つの要因によって引き起こされることが多いです。
1️⃣ 視覚認知の問題
→ 目で見た情報を正しく認識できない(形の恒常性や視覚弁別の弱さ)
2️⃣ 運動制御の問題
→ 手の細かい動きをコントロールできない(鉛筆の操作が不安定、筆圧が弱すぎる・強すぎる)
左の画像にある十字矢印がバラバラに描かれているお子さんの例は、目と手の連携がうまく取れていないことが原因と考えられます。
✅ VMIトレーニングで改善すること
VMIの改善には、適切なアセスメントと支援ストラテジーが重要です。
適切なトレーニングを行うことで、以下のような変化が期待できます。
🔹 線の書き方が安定し、正しい形を再現できるようになる
🔹 漢字のバランスが整い、書字の正確性が向上する
🔹 図形を正しく描けるようになる(算数・理科・美術の学習で有利)
🔹 工作や折り紙の精度が上がる
🔹 スポーツの際に、視覚情報を基にした素早い動作が可能になる
✅ VMI改善のためのアプローチ
• 模写トレーニング(簡単な図形からスタートし、段階的に難しくする)
• 書字トレーニング(点線やマスを活用して正しいバランスを習得)
• 定規やコンパスを使った作図練習
• 迷路やパズル(目と手の連携を強化)
• スポーツやリズム遊び(ボール投げ、なわとび、手遊びなど)
適切な支援とトレーニングを行うことで、VMIの能力は大きく向上し、学習や日常生活のパフォーマンスが改善されます。
視覚運動協応は、「書くこと」だけでなく、「学び・遊び・運動」すべての場面に影響を及ぼす重要なスキルなのです。



視知覚トレーニング6か月後:模写検査(VMI 視覚運動協応)
6か月間の視知覚トレーニングを経て、矢印の向きや角度の正確性が向上し、視覚情報を適切に処理する力が強化されました。
視覚運動協応(VMI)の改善により、目で見た情報を正しく認識し、それを手で表現する能力が向上したことが伺えます。
✅ 改善のポイント
• 線の方向・角度の誤りが減少し、より正確な形を再現できるようになった
• 視覚的なフィードバックを受けながら修正する能力が向上した
• 視覚認知力の向上により、形の恒常性や空間認識の発達が見られる
このような変化は、書字や学習、運動などのあらゆる場面でのパフォーマンス向上につながります。
三直線の交差課題における視覚運動の困難性
視覚運動協応(VMI)の評価において、三直線の交差課題では、斜線の認識・傾き・交差の理解に課題が見られるケースがあります。
この場合、線の位置関係が正しく認識されず、バラバラな形として表出されることが特徴です。
✏ この状態が学習に与える影響
• ひらがな・カタカナ・漢字はすべて線の組み合わせで構成されているため、書字や文字の認識が困難になる
• 黒板の文字をノートに正しく写すことが苦手になり、板書に時間がかかる
• 文字の形を覚えにくく、新出漢字の習得が遅れがちになる
• 図形を正しく描くことが苦手になり、算数の作図や幾何学的な課題で苦戦する
✅ 対策・トレーニングアプローチ
• 線の模写トレーニング(単純な直線から徐々に交差を含むものへ)
• 視覚認知強化(形の恒常性・空間認識の向上を促す課題)
• 運動制御トレーニング(鉛筆のコントロール、筆圧の調整、目と手の協応を鍛える)
視知覚トレーニング6か月後 - 模写検査(VMI 視覚運動協応)
視知覚トレーニングを継続的に実施した結果、以下のような顕著な改善が見られます。
✅ 変化のポイント
• バラバラだった線の交差が正確に描けるようになった
• 傾きや角度の認識が向上し、図形の再現が安定してきた
• 線の長さや配置のバランスが整い、全体的にまとまりのある形を描けるようになっている
✏ この変化がもたらす効果
• ひらがな・カタカナ・漢字の書字がスムーズになり、学習効率が向上
• 板書が速く、正確にできるようになり、学校の授業に適応しやすくなる
• 算数の作図や図形認識の精度が向上し、学習全般にプラスの影響
• 目と手の協応がスムーズになり、スポーツや日常生活の動作にも良い影響を与える
📌 視知覚のトレーニングは、「見え方の質」を向上させ、学習や日常生活の困り感を軽減する大きな鍵となります。
継続的なアプローチによって、さらに高いレベルでの視覚運動能力の向上が期待できます。
結果の解釈 ー 視機能と視覚情報処理の総合分析
視機能アセスメントでは、眼球運動・屈折検査・両眼視機能検査などの「入力系」の評価と、**TVPS-3などの「視覚情報処理能力の検査」**を総合的に分析し、お子さんの状態像を詳細に解釈します。
🧐 状態像の見立てと分析プロセス
見立てには、単一の検査結果だけでなく、以下の要素を統合的に考慮します。
✅ 生活・学習場面でのエピソード
→ 日常の行動や学習時の困り感、保護者・教育機関からの情報を考慮
✅ 検査場面での行動観察
→ 目の使い方・姿勢・集中度・タスクへの取り組み方を観察
✅ 各種検査結果の相関分析
→ 「視覚入力」「情報処理」「出力(運動・書字)」の関係性を検討
これらを熟慮し、複数の仮説を立てた上で、最も矛盾のない結果を導き出すことを重視します。
🚨 検査結果がラベル付けにならないように
時折、知能検査や発達検査の結果が「方策の提示」なしに伝えられ、お子さんのラベル付けにつながってしまうケースが見られます。
本来、検査とは「困り感の裏付け」ではなく、「困り感を覆すための戦略を見出すためのもの」であるべきです。
💡 だからこそ、視機能と視覚認知のアセスメントは重要です。
これらの検査は、お子さんが本来持っている資源を最大限に活かし、環境調整や適切な支援を提供するために行うものです。
🔍 結果解釈のゴール
✔ お子さんの視覚的困難を可視化し、適切な支援方針を立てる
✔ 単なる「診断」ではなく、具体的な「方策」としてアウトプットする
✔ お子さんが本来持っている能力を最大限に発揮できる環境を整える
「見えにくさ」や「学習の困難」を正しく理解し、視機能・視覚認知の専門的な視点から、より良い解決策を導き出すことを目指します。
📌 よくあるご質問(FAQ)
Q1. 視覚認知検査は、医療機関や学校・療育施設の紹介がないと受けられませんか?
A. 原則として、医療機関・学校(通級教室含む)・療育施設からの紹介を優先させていただいております。
🔹 理由
検査には「主訴(困り感)」が重要であり、知能検査・発達検査の結果や学習・行動観察を踏まえた紹介の方が、より適切なアセスメントが可能になるためです。
また、紹介があった場合でも、視機能以外の要因が疑われる場合には、より適した他機関をご案内することがあります。
📌 対象年齢
✅ 7歳~高校生
✅ 6~8歳未満のお子様は、事前に必ず医療機関で疾患の有無を確認した上でご予約ください。(弱視などの治療が優先される場合があります。)
📌 対象となるお子様
✅ 限局性学習症(LD)、自閉症スペクトラム、注意欠如・多動症(ADHD)などの神経発達症候群(発達障がい)を持つお子様
✅ 診断がなくても、ご家庭や学校で学習・生活に困難を感じているお子様
Q2. 視覚認知検査を受けるには、知能検査の結果が必要ですか?
A. 必須ではありませんが、可能であれば事前に受けておくことを推奨します。
📌 理由
視覚認知検査は「視機能・視知覚」の困難を評価するものですが、「読み書きが苦手」という主訴の背景には、認知機能やワーキングメモリー、音韻処理など、視覚以外の要素が関与している可能性もあります。
🔹 知能検査の結果があると、視機能以外の要因との関連を整理しやすくなるため、より的確なアセスメントが可能になります。
Q3. 知的障害がある場合、視覚認知検査は可能ですか?
A. 知的能力の水準やコミュニケーション能力によっては、実施が難しい場合があります。
📌 実施が困難なケース
✅ 知的能力が重度で、言語的コミュニケーションが難しい場合
✅ 多動の特性が強すぎて、検査中の集中が維持できない場合
📌 対応可能なケース
✅ フォーマルなアセスメントが難しい場合でも、インフォーマルな評価(行動観察・複数の簡易検査の組み合わせ)による評価は可能です。
✅ 環境調整(静かな部屋での実施・時間の調整)や、保護者の協力があれば実施できるケースもあります。
実施可否については、事前にご相談ください。
Q4. 眼鏡やビジョントレーニングで、読み書きの困難は改善しますか?
A. 背景に視機能の問題がある場合、眼鏡やトレーニングで改善する可能性は高いですが、それだけですべてが解決するわけではありません。
📌 読み書きの困難の要因
読み書きのスキルは、以下のような要素の組み合わせで成り立っています。
✅ 視機能・視知覚(眼球運動・両眼視機能・視覚認知)
✅ 音韻処理・ワーキングメモリー(言語的な処理能力)
✅ 運動協応・注意力(鉛筆操作・書字スキル)
視機能の弱さが原因であれば、眼鏡補正やトレーニングで改善できますが、他の要素が関与している場合は、教育現場での配慮や他の専門機関での支援も必要になることがあります。
📌 視機能が改善すると得られるメリット
✅ 「読む」「書く」に関する負担が軽減し、学習の質が向上する
✅ 文字のダブりやブレが軽減し、視線移動がスムーズになる
✅ スポーツや空間認識の精度が向上する
完全な「治療」ではなく、視機能の問題という「鎖」を1本でも外して、より学びやすい環境を作ることが目的です。
Q5. ビジョントレーニングの効果は?
A. 眼球運動や視覚処理の向上により、「読む・書く・図形の理解・球技などのスポーツ」における困難の軽減が期待できます。
📌 トレーニングによる具体的な変化
✅ 文字が安定して見えるようになり、読み書きの負担が軽減
✅ 板書やノート写しのスピード・正確性が向上
✅ 図形や空間認識の精度が上がる(算数・理科・美術で有利)
✅ 球技(野球・サッカー・バスケ)などで、動く対象への反応が向上
学習や生活の中で「できた!」という経験を増やし、お子さんの自信を引き出すことが、ビジョントレーニングの大きな目的です。
📌 当施設でのトレーニング方針
✅ 「成功体験」「達成感」を重視し、自らタスクに挑戦できる環境を整える
✅ 一方的な訓練ではなく、楽しく取り組めるプログラムを導入
✅ お子さんの個々の特性に応じたオーダーメイドの支援
「成功体験」「達成感」「自らがタスクに挑む力」は、生きていく上での重要なスキルです。視覚機能を通じて、それらを育むサポートを行います
まとめ
👓 視覚認知検査は、「ラベル付け」ではなく、「方策を見出すため」のもの。
👓 視機能と視覚認知を評価し、学習や生活の困難を軽減する。
👓 適切な眼鏡補正やトレーニングで、視覚の問題を改善し、学習・運動のパフォーマンスを向上させる。
👓 ビジョントレーニングは、視機能の向上だけでなく、お子さんの「成功体験」「挑戦する力」を引き出す。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
【重要】小・中学校及び療育施設からのご紹介方法についてのお願い
【ご紹介に際してのお願いと背景】
-
見立ての曖昧さによる混乱
適切な事前情報・視点が共有されないまま、「読み書きが苦手なので、視覚の評価を!!」といった“部分的・推測的な見立て”の段階で当方が関わると、評価結果が独り歩きし、かえって混乱を招くことがございます。 -
リソースと費用構造の無視
当方の評価には、専門的な人的資源・時間的コストが多大にかかっております。
そのことに触れず「紹介」の形で親切心だけを前面に出されると、支援者の善意の一方的消費となり、支援構造の持続性が損なわれます。 -
情報だけを持ち帰る関わり方の危険性
「とりあえず見てもらって検討」といった形は、当方が意図する“視覚支援としての一貫性”を損ね、ご本人やご家庭の混乱・期待落差を生むケースが少なくありません。
【お願い】
ご紹介の際には、以下の点をご確認いただきますようお願いいたします。
-
対象となるお子様が困り感や視覚支援の必要性を感じていること
-
ご紹介者が評価や相談には、原則として費用が発生することをご本人(ご家庭)に明確に伝えていること
-
ご紹介者として「見立ての段階」と「ご依頼内容の具体性」を十分に把握しておられること
※上記が不明確な場合は、検査依頼自体をお断りさせていただく場合がございます。何卒ご理解いただければ幸いです。
無責任な“紹介風”の依頼は、一見すると善意に見えるかもしれません。
しかし実際には、現場の人的・精神的リソースを著しく浪費させ、支援構造そのものを崩壊させる原因となっています。
これ以上、“誰も責任を取らない善意”により、支援者が疲弊し、誤解や混乱が拡がっていく構造を容認することはできません。
私たちは、限られた時間と体力と誠意を、「本気で支援を求める方」へ全力で注ぐために、今後、曖昧で一方的な紹介や、軽視された依頼については、すべてお断りさせていただきます。
誠実な支援と連携を継続するために、構造の見直しと責任の共有を強くお願い申し上げます。