『困り感』って、誰の困り感?
- ジョイビジョン奈良.OptMatsumoto(1級.眼鏡作製技能士)

- 2025年10月17日
- 読了時間: 3分
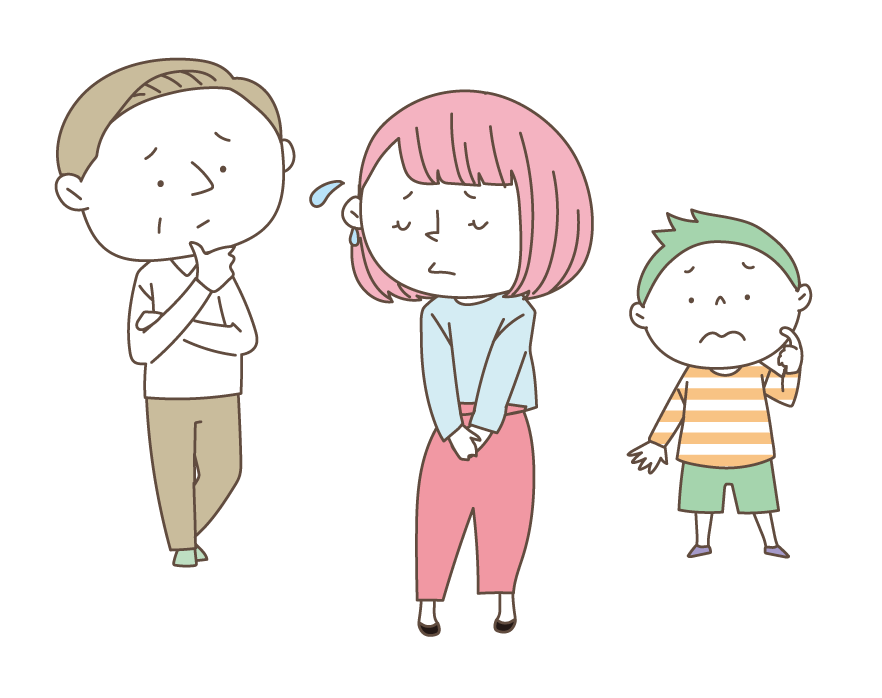
支援や教育の現場でよく使われる言葉に「困り感」というものがあります。
しかし、この「困り感」は実は非常に主観的で不安定なものです。
困り感とは、「ある課題や状況に対して、本人が“うまく適応できない”と感じている主観的体験」を指します。
重要なのは、“他者が見て困っているように見える”ことと、“本人が困っていると感じている”ことはまったく別物だという点です。
たとえば、「話を聞いていない」「注意がそれている」ように見える子どもがいたとしても、それは本当に“本人が困っている”状態なのか?
あるいは、周囲が決めた環境・ルール・期待の枠から外れているという理由だけで“困っているはず”とみなしてはいないか?
実際には、本人は困っていないこともあるし、もっと言えば、困っていることにすらまだ気づいていない段階かもしれない。
この「気づいていない段階」を、心理学では“前意識レベル”と呼んだり、発達支援の分野では“未分化”ととらえることもあります。
この段階では、支援者が勝手に「困っている」とラベリングしてしまうと、それがそのまま“本人の物語”になってしまう危険があります。
Ⅱ. 「誰の問いなのか」
では、そもそもその「困り感」という問いは、誰の中から立ち上がったものなのか?
この視点は、現象学で重要とされる観点です。
現象は、「誰のまなざしから語られているか」によってまったく意味が変わります。
教師が感じた「困り感」、親が感じた「困り感」、支援者が見出した「困り感」
それらはすべて、“本人ではない誰か”の視点から立ち上がったものです。
そして、その「まなざし」が強く作用するほど、本人の内的世界は、“他者の解釈”に置き換えられていきます。
つまり、その問いは、本人のものなのか?それとも、周囲の誰かが必要として立てたものなのか?
この問いの立ち位置を見失うと、支援は簡単に「意味のすり替え」「他者視点の押し付け」に変わってしまうのです。
Ⅲ. 困り感は、“構造化された問い”として扱うべきもの
「困っているかどうか」は、評価ではなく“問い”である。
そしてその問いは、常に構造化された文脈の中で扱われるべきだ。
その困り感は、誰の視点から立ち上がったものか?
本人はそれを、どう感じているのか?
それは、本人にとって“言葉になっている”のか?
それとも、“まだ言葉になっていない素材段階”なのか?
その問いが“誰のためのものか”を、支援者は自覚しているか?
この構造を見失えば、本人がまだ言葉にできていない違和感を、他者の言葉で「定義」し、
「課題」「困難」として固定してしまうことになります。
Ⅳ. 結論──問いの出どころに立ち戻る
「困っているように見えるから、支援が必要だ」
これは一見、優しいまなざしのようでいて、実はとても強い意味操作を含んでいます。
だからこそ、あえてこう問い直したい。
その「困り感」は、誰が困っているのか?
本当に本人の中から立ち上がった問いなのか?
その問いが、本人の人生にとって意味ある言葉として届くためには、私たちはどこに立って、何を見ている必要があるのか?
こうして問いを組み直すことで、困り感は「呪い」ではなく、本人の中にある「違和感の声」をすくい上げるきっかけになるかもしれません
。




コメント